ここでは主に子育てや教育、対人支援について思うことや考えていることを書いています
 news
news 『〈叱る依存〉がとまらない』を読まれたDV加害更生プログラム参加者さまからのご感想がただただうれしかったというお話
拙著『〈叱る依存〉がとまらない』を読まれた元DV加害男性から、出版元経由で感想のメッセージを頂きました。頂いた内容があまりにもうれしいものだったので、ご本人に許可を頂いてこちらで紹介させて頂きます。
 news
news 渾身の社会課題提起本『〈叱る依存〉がとまらない』の”はじめに”を全文公開します
『〈叱る依存〉がとまらない』という本を出版させていただくことになりました。「だれもが生きて生きやすい社会をめざす」ための、渾身の力を込めた私なりの社会課題提起です。この本に込めた想いや願いをお伝えするために、出版元の紀伊國屋書店さまに「はじめに」を全文公開するご許可をいただきました。是非ご一読いただき、この問題についてともに考えていただけますと幸いです。
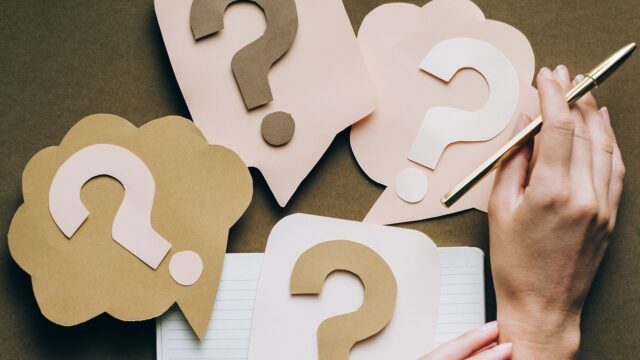 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 コグトレ記事への批判的考察③ー結局何が問題なのか
「認知機能」をトレーニングする、と言うからには、人の認知のメカニズムがどのようなものなのかを最低限でも知っておく必要があるはずです。例えば、視覚情報処理のメカニズムは、神経科学的にも認知科学的にも研究知見が進んでいる領域であり、その気になれば学べる良書、テキストがたくさんあります。その他の認知機能についても同じです。その努力すらする気がないのに「子どもたちの認知機能をトレーニングする」なんて取り組みをするべきではないと思うのです。
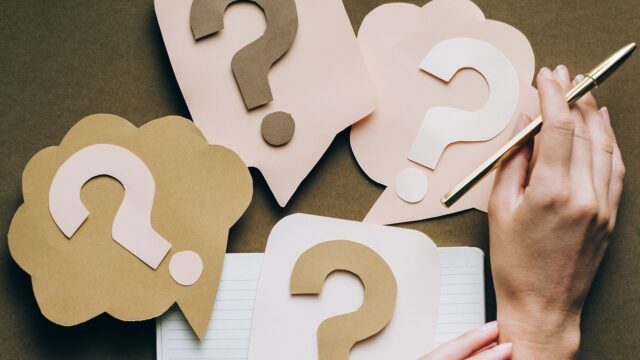 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 「コグトレ」記事への批判的考察②ー「認知機能」の便利使い
今回は、具体的に「コグトレ」において認知機能という言葉がどのように便利使いされてしまていると考えられるのか整理し、何が問題なのかについてお伝えできればと思います。
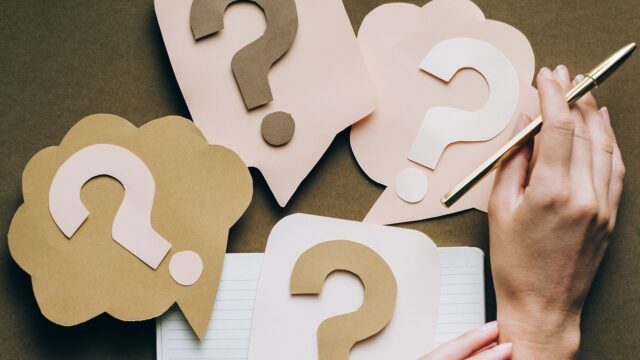 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 「コグトレ」記事への批判的考察
今まであまり批判的な記事を書くことはなかったのですが、先日公開されたコグトレ(認知機能トレーニングについての愛称みたいなものです)記事の内容が「いくらなんでも...」という内容だったので、批判的な論考記事を書きたいと思います。
 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 「言葉の定義にこだわる」大切さを改めて考えてみた
「言葉の定義にこだわる」ことについて、改めて考えて思うところを書きたいと思います。このことは、人とのコミュニケーションがうまくいかない背景要因として、実は大きな影響力のあることだと思っています。
 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 「認知」という言葉 重要な2つの定義
「認知」という言葉。この言葉を対人援助領域や教育領域で専門用語として使用する場合、絶対に押さえておきたい定義として少なくとも大きく2つの定義、つまり「言葉の意味」があります。
 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 イヤーマフをもっと普及させたいと思う話
なぜもっと普及しないのだろうと不思議に思ってる「イヤーマフ」について書きたいと思います。息子を見ていて思うのは、イヤーマフがあるということ自体が息子にとってのお守りみたいな役割の安心材料になっていたということ。
 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 理不尽への「我慢の強要」と「学習性無力感」について②
今回は忍耐力とは何か、忍耐力を身につけるために必要なことや有効なことは何かということについて、私なりに整理して書きたいと思います。
 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 理不尽への「我慢の強要」と「学習性無力感」について①
先日、理不尽への我慢の強制について書きツイートをしたところ、たくさんの反響を頂きました。このテーマについてはいろいろ思うところもありますので、ブログにまとめたいと思います。