 news
news渾身の社会課題提起本『〈叱る依存〉がとまらない』の”はじめに”を全文公開します
『〈叱る依存〉がとまらない』という本を出版させていただくことになりました。 「だれもが生きて生きやすい社会をめざす」ための、渾身の力を込めた私なりの社会課題提起です。この本に込めた想いや願いをお伝えするために、出版元の紀伊國屋書店さまに「はじめに」を全文公開するご許可をいただきました。是非ご一読いただき、この問題についてともに考えていただけますと幸いです。
 news
news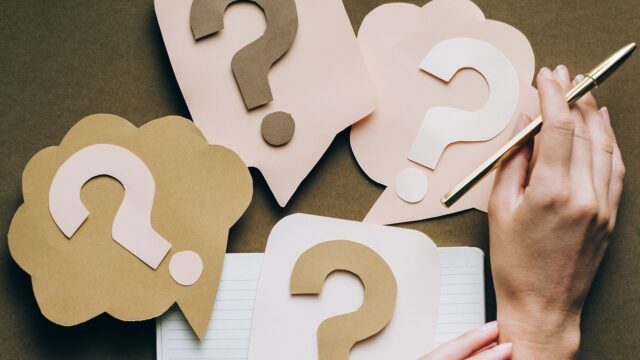 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳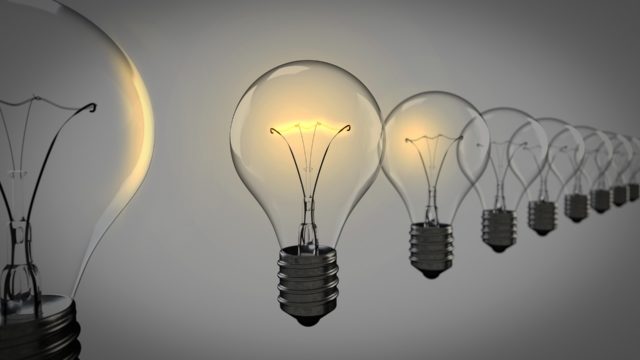 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳 心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳
心理士パパの子育て、教育、対人支援もろもろ雑記帳