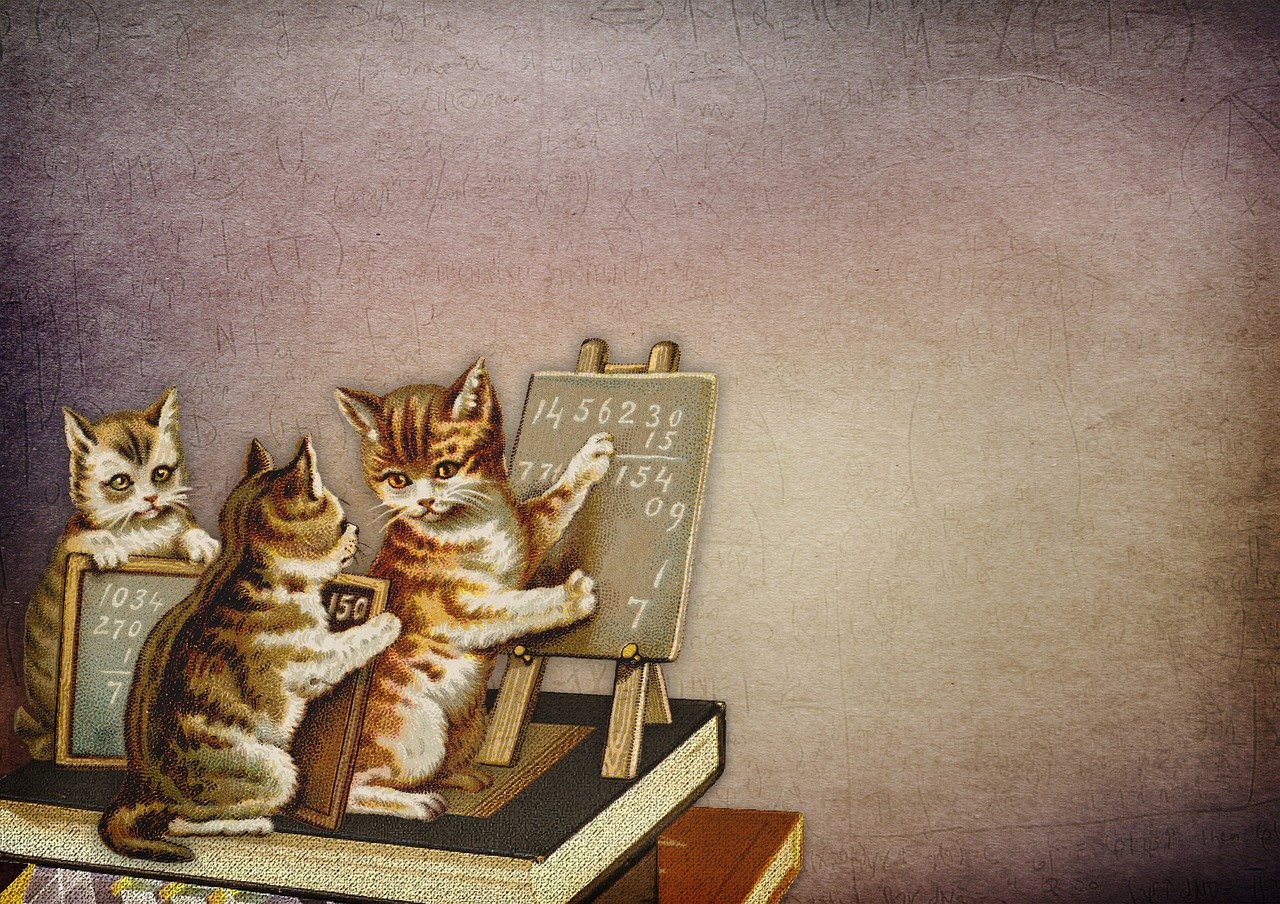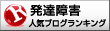こんにちは。
ほんとうに久しぶりの記事になりましたが、今回は「日本人のIQ105問題」について書きたいと思います。このテーマ、誤った根拠による「選民思想」や、「人種差別」にもつながりかねない、根深い、いや闇深いとでも表現すべき問題のようです。ぜひ多くの人に知ってもらいたいと思っております。
そもそも本来「平均IQ105」はありえない
最近になってSNS(主にtwitter(現:X))の投稿や広告に、ちらほと「日本人の平均IQ105」という文言を目にするようになりました。日本人のIQだけでなく、世界地図の上にそれぞれの地域ごとのIQが表記された図表が拡散されていたりするのです。
その度に私は、「なんだこれは?」と不思議な気持ちになっていました。なぜならば、日本に限らず「平均IQ105」なんてことは、本来あり得ない話だからです。
ご存じの方も多いと思いますがIQ(Intelligence Quotient)は、日本語で知能指数と呼ばれる、人間の知的能力を測るための指標です。IQは通常、知能検査と呼ばれるテストをすることで計測されます。世界的によく使われている知能検査には、たとえばWAIS(大人用)やWISC(子ども用)などがあります。重要な知識として、こういった国際的に使用される知能検査はリリースされる前に、必ず現地にてたくさんのデータを集め、その結果を根拠数値として用いている事実があります。例えば日本で使用される知能検査は、日本人を対象としたデータを集めてそれを用いているわけです。
だから当然「日本人の平均IQは100」です。
むしろ発想が逆で、日本人のデータを集めてその平均が100になるようにIQを算出する計算式が組まれているわけです。当然、どこの国の知能検査でも自国民のデータを集めて平均IQが100になるように、ローカライズされています。
逆に言えば、国や地域を越えた「人類共通のIQ測定法」は、存在していないのです。国や地域によって使用する言語や文化が大きく異なりますので、共通する測定手法を作ることが不可能だからです。日本で用いられている知能検査は当然日本語で実施され、かつ日本において「常識」とされる内容を含んだ検査内容になっています。もし日本にローカライズされた検査が存在しなければ、外国語で実施され日本の文化とは異なる文脈の検査内容が含まれた知能検査が用いられることになります。それでは、正しくIQを計測することな出来ないことは、想像に難くないことですよね。
ここまでの話をご理解いただけるだけで、私が「日本人の平均IQ105」に首を傾げた理由がお分かり頂けるかと思います。私が不勉強なだけで、何かIQの国際比較ができる革新的な方法が開発されたのか?などといろいろなことが頭を巡りました。
ソースは『知能の人種差』という書籍?!
「一体、どういうことなのだろう?」
不思議に思った私はtwitter(現X)で、このことについての情報を呼びかけてみました。その結果、非常に重要な情報を得ることができたのです。それは一冊の本が、『元ネタ』になっているのではないか、という指摘です。
本のタイトルは「Race Differences in Intelligence:An Evolutionary Analysis(知能の人種差:進化論的分析)」というもので、2006年に初版が出版され2015年に第二版となる改訂版が出版されています。
著者はリチャード・リンというイギリスの心理学者で、この方は自身を「科学的人種差別主義者(scientific racist)」と称する人物です。(他者からの呼び名ではなく自称なので、人種差別をしてもよい理由を科学的に研究しているという自認があったということなのでしょう)この事実だけでも本テーマが、人種差別や排外主義に直結し得る非常にセンシティブかつ重要なテーマであることが、お分かり頂けるかと思います。彼は「科学的な研究」によって、「人種間には遺伝的に決定された平均知能の有意な差」が存在することが確認されたと主張し、そのことが世界的な不平等の主要な原因であると結論づけました。そしてこの「知能の人種差」という本は、彼の代表作とされる著作のようです。
気になって調べてみたところ、彼の研究は、その方法論、データの解釈、そして結論において主流の科学者から激しく批判されており、しばしば疑似科学として分類されている ようです。つまり彼は、白人至上主義的な思想の持ち主であり、人種差別的なイデオロギーを維持するための証拠として、自分の研究業績を用いる人物だと言えるでしょう。彼の研究成果が、科学的に見て妥当なものであれば、まだ議論が成立するのかもしれませんが、どうやら彼は恣意的に研究をねじ曲げて持論の根拠としていたのです。
かなりデタラメな『知能の人種差』
さて、ここからは疑惑の書籍『知能の人種差』の中身に迫っていきたいと思います。
私は2015年に出版された改訂版の全文データを手に入れて、本書の内容を読んでみました。(インターネット上に公開されていますので、誰でも手に入れることが可能です)
私の第一印象は「これが許されるのならば、研究と称してどんな主張でもできてしまう」というものでした。どこからつっこんでよいのやらと思うくらいに、論理の飛躍や研究手法上の問題点が山積みだったからです。
長くなってしまいましたので、この本にどんなことが書いてあるのか、また具体的に何がどのように問題なのかについては、続編として書きたいと思います。まずは本問題の存在について、多くの人に知っていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。